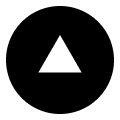“属人化”を脱却し営業を強化する – Salesforceを活用した営業活動の仕組化をご支援

目次
鯖寿司や昆布巻きなどの和惣菜を中心に、製造から小売まで一貫して手がける老舗食品メーカーである株式会社三徳。地域に根ざしたブランド「さんとく三太郎」を展開しつつ、自社工場の設立や業務DXを推進するなど変革の真っ只中にあります。
そうした中、課題となっていたのが営業活動の属人化でした。「展示会での名刺フォローが追いつかない」「商談の進捗が社内で共有できていない」といった状況を打開するために、今回ストラが営業プロセスの仕組化とSalesforce導入をご支援させていただきました。
今回は代表取締役社長である大澤様に、Strhとの取り組みや支援を受けた背景、Salesforce導入後の変化について詳しくお話を伺いました。
老舗食品メーカーの転換期と“属人化”の壁
最初に貴社のご紹介と事業領域について教えてください
大澤様:弊社は食品製造工場と、小売店舗「さんとく三太郎」の経営をしております。もともとは私の父が立ち上げた食品メーカーで、創業から数十年にわたって海外の委託工場で生産した和食材を輸入卸するという形で事業を展開してきました。代表的なのは鯖寿司や焼き魚、昆布巻きなどの“和惣菜”と呼ばれるジャンルの食品です。輸入卸という形で販売を行う一方、自社ブランドとしても“さんとく三太郎”という名前で商品をリリースしており、地域の方々からは“老舗メーカー”というイメージを持たれていました。
内山:輸入卸から始まり、今では自社ブランドまで幅広く取り扱われているのですね。近年はコロナ禍など外部環境が大きく変化しましたが、御社でもやはり影響が大きかったでしょうか?
大澤様:コロナ禍では海外との輸送コストや流通リードタイム、さらには衛生面に対する消費者意識などが大きく変わり、従来のビジネスモデルでのリスクを強く感じたのと、もともと父の代から『いつかは国内で安定して作れる体制を整えたい』という想いはあったので、コロナ禍をきっかけに“やるなら今だ”と方向転換をしました。
具体的には、県内に自社工場を設置して品質管理や製造工程を一から再構築し、OEMで受注していた加工食品も国内で完結できるようにしました。結果として“国産の安心感”を打ち出しやすくなり、近隣地域のスーパーや専門店との連携も強化されました。
ただ、生産管理や事務処理などの効率化は進んだ一方、営業面だけはどうしても私個人が属人的に担当してしまっていて……。

今回CRM・SFAの導入を検討された背景を教えてください
内山:工場や事務のDXがある程度進んだ中で、営業活動はまだ属人的だったんですね。それが今回Salesforceを検討されるきっかけにもなったと伺っています。
大澤様:その通りです。私自身、経営者として会社全体を見る立場になった直後は、営業の属人化がそこまで深刻だとは思っていなかったんですが、展示会に出展した際に集まる名刺の数が増えても、フォローアップがまったく追いつかない。
同時に、新規のお客様へ提案する時間が取れずに、結果的に機会損失を起こしていると気づいたんです。しかも事務所内でも、『あの商談、いまどこまで進んでいるんですか?』と聞かれても私しかわからない状態。このままでは拡大路線に乗せられないと、本格的に課題感を持ちました。

DXシステム導入のハードルと営業プロセスの強化
Salesforceを導入されたきっかけを教えてください
大澤様:お恥ずかしながら最初は名前くらいしか知らなかったんです。Salesforceというと私のイメージでは「外資系の大企業向けシステム」という印象が強くて、自社規模で使いこなすことなんて想像できなかったんです。
それがある日、SNSの広告で「中小企業向けに特化した導入支援」や「2億円の壁を突破するためのSFA活用」といったキャッチコピーを見かけて、気になって資料を取り寄せてみたりしました。
そして、Salesforce社の担当の方から『実際に同じ課題を持つ中小企業のお客様も多く導入して成果を上げている』という話を聞けたんです。それに加えて、当時ちょうど「滋賀県未来投資総合補助金」という補助金制度がありました。DX関連の設備投資に対して補助金が出るとのことだったので、思い切って「まずは補助金の申請が通るか」を商工会に相談したんです。
内山:滋賀県未来投資総合補助金、私も後から知りましたが、なかなか魅力的な制度ですよね。最大で何割ほど補助を受けられるんでしょうか?
大澤様:通常枠であれば上限50万円、補助率は1/2という感じですね。弊社が申請したのは、DX関連の生産性向上を目指す枠組みでした。一度申請書類を作ってみたら、商工会の職員さんが丁寧にアドバイスしてくださって、結果的にスムーズに通りました。補助が出るとわかると、本当に導入のハードルがグッと下がります。
Salesforceを導入を行っている企業が多くある中で、Strhの支援を受けるに至った決め手は何でしょうか?
大澤様:Salesforce社の担当者さんと話を詰めていく中で『システム構築だけじゃなくて営業プロセスの整備を一緒にやってくれるコンサルティング会社がありますよ』と紹介されたのがストラさんでした。私は「単にシステムを導入するだけ」では解決しないと思っていたので、この営業プロセス面でのご提案に強く興味を惹かれました。
内山:ありがとうございます。当社は外資系コンサルティングファームで大企業のCRM導入を支援していたメンバーが中心ですので、「システム構築×業務支援」の両面をカバーできるのが強みです。大澤様が抱えられていた“属人化を解消したい”という課題に対して、まずどのような業務フローが理想か、そこからシステムであるSalesforceに落とし込むというアプローチを取らせていただくとご提案差し上げました。
大澤様:まさにそれです。うちは大企業みたいに「すでに営業の仕組みが整っている」わけではなく、私の頭の中にだけ経験値や取引先の情報が蓄積されている状態でしたからね。この部分を洗い出しながらシステム化できるなら、そりゃ助かるぞと。
業務面も含めたプランニングとクイックなプロトタイピング
今回のプロジェクトの進め方を振り返って、いかがだったでしょうか?
大澤様:補助金事業の都合もあり、年内に「運用開始ができる形」にしたかったので、およそ2か月間の短期集中でかなりタイトなスケジュールでした。ただ、御社が毎週定例のミーティングを設定してくださったので、細かい疑問を速やかに解決しながら進められた印象があります。
内山:最初のステップとしては、業務面から「As-Is」の洗い出しを行いました。つまり、いま大澤様が営業活動をするとき、どのような流れで見込み客が生まれて、見積を出して、契約・納品を行っているのか。それをできる限り細かくヒアリングしフローチャート化させていただきました。
ここで大切なのが、属人的に行われている判断基準や連絡手段をできるだけ言語化すること。『この書類っていつ作るんですか?』『このステップでメールを送っているのはどんなタイミング?』といった具合に、普段は頭の中だけで完結していることを全部リストアップさせていただきました。
大澤様:正直あれは大変でした(笑)。でも、やり始めると「あ、そういえばこのタイミングでサンプル発送して、相手から返事をもらったら別の担当者と一緒に訪問していたな」とか思い出すんですよ。そういった工程が可視化されると、『この部分は他の人でもできるな』という気づきも得られました。まさに属人化の解消に向けた第一歩だった気がします。
内山:それらの内容を踏まえてシステム導入後の業務としての「あるべき姿」をデザインしました。すなわち、理想の営業プロセスをステージに分け、Salesforce上で管理する仕組みです。
例えば、展示会で名刺をもらったら「リード」として登録し、一定期間内にフォローがなければ自動的にリマインドが通知される。商談化した段階では「提案ステージ」に切り替わり、見積書の提出状況やお客様とのやり取りをSalesforce上に記録していくなど、流れを一つひとつ整理しました。
大澤様:毎週のミーティングでプロトタイプをお見せいただきながら、「ここはもうちょっと簡単に入力できないですか?」とお伝えしたら、すぐに修正をしていただけるので、私のようにシステムにあまり慣れていない人間でも「こうすれば使いやすい」と思う点を伝えられて助かりました。

今回のプロジェクトのポイントはどういったところでしたか?
内山:私たちも作り込んだ後で大幅に仕様変更するより、実際に触ってもらいながら都度ブラッシュアップしたほうが確実に運用しやすいシステムが構築できると考えています。構築観点では今回のプロジェクトで主に重点を置いたのは以下の三点です。
1.商談ステージ管理
- リード(見込み客)の発生源ごとに登録
- 提案ステージを段階的に切り替え、見積やサンプル発送履歴を一元管理
2.展示会フォローの仕組み化
- 名刺交換後、一定期間で未フォローの場合にタスク発行
- フォロー頻度や優先度を可視化して、機会損失を減らす
3.進捗の見える化
- 大澤様以外のスタッフでもお客様の状況がすぐに分かるようにする
- チャット連携やドキュメント共有で、営業が不在でも対応ができる体制へ
これらの要件を短期間で構築し、年内に運用がスタートできたのは、大澤様の積極的なフィードバックのおかげです。

大きな商機の獲得と業務効率化の実現
実際に導入から数カ月経った今、どのような変化がありましたか?
大澤様:ありがたいことに年末から年明けにかけて、新規のお問い合わせで案件が立て続けに入りました。しかも、そのうちの1件は当社としてもかなり大きめのロットの発注になりそうです。もちろん、営業としては喜ばしいことですが、製造側がまだ新ラインの稼働最適化に手間取っていたりしています。現状私自身もそちらの調整に時間を取られてしまっています。
ただ、Salesforce上に今回の商談記録や相手先の要望、納品スケジュールなどをこまめに記録しているので、仮に私がすぐに対応できなくても、事務スタッフが「今このお客様はサンプルを受け取って返事待ち」だとか、「工場視察の日程調整が必要」だといった情報を確認できます。やはり『属人化』が解消され、情報が社内にリアルタイムで共有されることで、急な状況変化にも対応しやすくなりました。
以前のように私個人の頭の中だけで管理していたら、「あ、連絡が滞っていた」なんてことが頻繁に起きていたでしょうね。

今後営業担当を増やして対応する計画などはありますか?
大澤様:今、具体的に追加採用も視野に入れ始めています。これまで私一人だったので、どうしても「私だけがわかる知識」が蓄積されてしまったんですが、Salesforce上に商談履歴や取引先情報が整備されていれば、新たに入った人もすぐにキャッチアップできるだろうと期待しています。
また、補助金についても改めて思うのは、『地域の中小企業こそ活用すべき』ということです。私も最初は知らなかったし、「手続きが大変そう」と敬遠していました。でも商工会議所や商工会が丁寧にサポートしてくれて、県もDX推進を応援したい思惑があるからか、わりとスムーズに申請が通りました。
会社の方針にマッチしているなら本当に有効な制度だと思います。
内山:地方や中小企業のDXはまだまだ伸び代があるとも感じます。今回のように補助金を利用できれば、導入コストを抑えつつ実質的な営業改革が進むわけですからね。他の中小企業者様にもぜひ取り組んでいただきたいですね。
販路拡大へ向けたAI活用の可能性
今回導入されたSalesforceの運用が定着化された以降、さらに発展的な活用について具体的な構想はありますでしょうか?
大澤様:そうですね。私はAIとの連携にすごく興味を持っています。食品加工業は天候や季節イベント、地域の祭事などによって需要が大きく左右されるんですよ。例えば鯖寿司なんかは、夏場よりも秋冬が売れやすい、あるいは地域行事と結びついて注文が集中する時期がある……といった特性があって、これを人力で予想するのはなかなか骨が折れます。
Salesforceの中に受注や商談の記録を積み重ねていけば、そのデータをAIが分析して『今月は何件の追加受注が見込めるか』『どのタイミングで仕入れを多めにしておくべきか』といった示唆を得られるはずだと期待しています。今はまだそこまで具体的に連携の話は動き出していませんが、今後取り組みたいテーマですね。
内山:AI連携は確かに注目度が高い領域ですね。Salesforce自体も昨今はジェネレーティブAIとの連携など、さまざまな機能拡充を進めていますから、データが蓄積されればされるほど活用の幅は広がると思います。販路拡大についてはいかがでしょう? いま店舗を2つ持たれているとお聞きしていますが、直営店の展開やECなど可能性は様々あるのではないかと考えております。
大澤様:おっしゃる通り、ECサイトの拡充も今後の課題ですね。鯖寿司は日持ちがそこまで長くないので、クール便で発送する必要があるのですが、近年は「おうち需要」も増えているので、地方の名産品をオンラインで購入される方は確実に増えているはずです。
弊社の場合、まだEC自体は簡易的なものしかないので、Salesforceの顧客データと連携して、もっと効果的なキャンペーンやDMを打てるようになれば面白いと思っています。
製造ラインも既にある程度DX化を進めているので、需要予測→生産→出荷→顧客アプローチという流れを一気通貫で可視化できれば、生産ロスを最小限にしながら売上を最大化できるのではないかと感じますね。

“仕組み化”で変わる中小企業の未来と成功のカギ
今回のプロジェクトで感じていること、また同じ課題で悩む中小企業へアドバイスをお願いします。
大澤様:まず、やはり『属人化』は経営者が思っている以上に大きなリスクだということを改めて感じました。私の場合、展示会で名刺を集めても、その後のアクションを全部自分で管理していて、実はこれが大きな機会損失を生んでいたんです。
DXというと大げさに聞こえるかもしれませんが、『誰がやっても最低限の成果が出せる仕組み』を作るだけでも、一気に売上や効率は変わるんですよね。
そして、システム導入だけを頼むのではなく、今回のように『営業ノウハウのコンサル』まで包括的にお願いできるパートナーと組むのが大きなポイントだと思います。大企業での事例をそのまま中小企業に当てはめようとしてもうまくいかない場合があるので、当社のように『経営者自身が営業を兼務している』とか『複数部門を管掌している』といった事情を理解した上で、ノウハウをチューニングしながら設計してもらえるのは本当に助かりました。
また補助金についても強調しておきたいですね。私も最初は「うちのような小規模では申請が通らないんじゃないか」とか「書類作りが大変そう」と思っていましたが、商工会議所の方々や県の担当部署が予想以上に協力的で驚きました。『滋賀県未来投資総合補助金』のおかげで初期費用の不安がかなり軽減され、もっと早く知っていればよかったとすら思います。
ですから、同じような悩みを抱えている中小企業の皆さんも、一度は地域の商工会や補助金情報をチェックしてみてほしいです。意外と活用できる制度や施策があるはずで、「導入費用がネック」という課題も解決できるかもしれません。
私自身、まだまだこれから運用を磨いていく段階ですが、すでにSalesforce導入の効果を実感していますし、将来的にはAI分析やEC連携を含めてさらなる成長を目指したいと思っています。
内山:ありがとうございます。私たちストラとしても、今回のプロジェクトを通じて「弊社の大企業向けの業務・システム構築ノウハウが中小企業にも十分活用できる」ことを再確認しました。属人化の解消に向けて踏み出される企業は今後ますます増えていくはずですし、私たちもそのお手伝いを続けていきたいと思います。本日は貴重なお話、本当にありがとうございました。