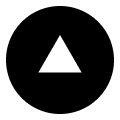【徹底比較】SFAとCRMの違いとは?営業・マーケ・導入担当者向けの選び方ガイド


この記事でわかること
- SFAとCRMとは何か
- 機能面、部門別、目的別からみるSFAとCRMの違い
- SFAとCRMを導入するメリットとデメリット
- SFAとCRM導入のよくある失敗原因
- SFAとCRMを定着化させる4つのポイント
- ツールの違いと選定基準

執筆者 代表取締役社長 / CEO 杉山元紀
マーケティングについてのお困りごとはプロにご相談ください
- 営業プロセスの可視化のためにツールを導入したいが、自社に合うツールが分からない
- 顧客管理の効率化のためにツールを導入したいが、自社に合うツールが分からない
- ツールを導入したが、使いこなせていない・定着化しない
営業活動や顧客管理の効率化を目指す企業にとって、「SFA」と「CRM」は今や導入が当たり前の存在になりつつあります。しかし、両者の違いや目的を明確に理解していないまま選定を進めてしまうと、機能が重複していたり自社の課題解決に繋がらない可能性もあります。
本記事では「SFAとCRMの違いがわからない」「自社に適したツールがどちらかわからない」といった悩みを持つ営業・マーケティング・情報システム部門の担当者に向けて、SFAとCRMの定義・役割から、機能面での違いや導入メリット・デメリットまで、実例や図表を交えながら網羅的に解説します。
読了後には自社にとって本当に必要なツールは何かを判断できるようになり、導入・活用の成功確度が大きく高まるはずです。ツール選定に失敗したくない方は是非ご覧ください。。
SFAとCRMそれぞれの内容について詳しく知りたい方は以下の記事を合わせてご覧ください。
参照:SFAとは?基礎知識からCRMやMAとの違いや導入ポイントをわかりやすく解説
参照:CRMとは?導入メリットや機能、選び方やおすすめツールまで解説
目次
SFAとCRMとは何かを正しく理解する
現代の営業・マーケティング活動ではデジタルツールの導入が不可欠となっています。その中でも「SFA(営業支援システム)」と「CRM(顧客関係管理システム)」は多くの企業で導入が進んでいますが、両者の違いを正しく理解していないまま活用しているケースも少なくありません。実際の多くの現場では同じ意味合いとしてSFAとCRMが用いられることもしばしばあります。
この章ではそれぞれの定義と役割、そして共通点と相違点を整理し基本的な理解を深めましょう。
SFAの定義と役割|営業支援に特化したツール
SFA(Sales Force Automation)は営業プロセスを効率化・可視化するためのツールです。具体的には案件管理や営業活動の進捗を一元管理し、営業パーソンの行動を定量的に把握できるようになります。
なぜSFAが営業部門で重要視されているのかというと、営業活動は属人化しやすく担当者の経験や勘に依存しやすい業務というのが一因です。SFAを導入することで営業の行動ログが蓄積され、ノウハウの共有・営業プロセスの標準化・KPI管理などの実現が可能です。
例えば、日々の訪問件数や商談ステータスの遷移などを可視化することで、課題の早期発見や改善に繋がり組織全体の営業力を底上げする効果も期待できます。
CRMの定義と目的|顧客との関係性を深める仕組み
一方でCRM(Customer Relationship Management)は、顧客との継続的な関係構築に主眼を置いたツールです。顧客の属性情報・購買履歴・問い合わせ履歴など、あらゆる接点を一元管理することで、パーソナライズされた対応やLTV(顧客生涯価値)の向上を実現します。
CRMが重要とされる背景には、新規顧客の獲得コストが既存顧客の維持コストよりも高いという事実があります。CRMを活用することで既存顧客との信頼関係を深め、再購入やサービス継続を促すマーケティング施策が可能になります。
また、CRMはカスタマーサポート部門やマーケティング部門とも密接に関わっており、リピーターの創出やクレーム対応の高度化にも効果的です。
SFAとCRMの違いと共通点を整理する
SFAとCRMはどちらも「業務効率化」や「情報の可視化」を目的としたITツールであり、機能が重なる部分も少なくありません。しかし、目的と使う主な部門が異なる点が最大の違いになります。
| 比較項目 | SFA | CRM |
|---|---|---|
| 主な目的 | 営業活動の管理・効率化 | 顧客関係の維持・LTV最大化 |
| 主な利用部門 | 営業部門 | カスタマーサポート・マーケ部門 |
| 管理対象 | 商談・行動ログ・KPI | 顧客情報・対応履歴・購買履歴 |
| 強み | 行動データによる改善・標準化 | 顧客満足度向上・リピート施策 |
SFAとCRMの導入を検討する際には、自社の業務課題や部門の役割を明確にしたうえで、どちらを優先的に導入すべきかを判断することが重要です。
SFAとCRMの違いを機能面から比較する
SFAとCRMは目的こそ異なるものの、どちらも業務効率化に貢献する強力なツールです。この章では「何ができるのか」「どこが得意なのか」といった機能面の違いにフォーカスし、それぞれが持つ強みをより深く理解できるように比較していきます。
営業活動の可視化に強いSFAと顧客接点の一元管理に優れたCRMについて、自社のニーズと照らし合わせながらそれぞれの得意領域を把握しておきましょう。
案件管理・営業活動の可視化はSFAの強み
営業活動においては「どの顧客に、誰が、いつ、何をしたか」といった行動履歴が非常に重要です。SFAはまさにこのような情報を蓄積・分析し、営業活動の見える化を実現します。ここからはSFAで実現できる代表的な内容をいくつかご紹介します。
営業プロセスの標準化と行動ログの取得
SFAを導入する最大の利点は営業プロセスの属人化を防げる点です。訪問・電話・メールなどの接触履歴を営業担当者が記録することで、業務の流れを統一化し組織的な営業体制が築けます。また、行動ログが残ることで、管理職によるフィードバックやマネジメントも容易になります。
アプローチ履歴や商談ステータスの一元管理
営業が進行中の商談に関しても、SFA上で「どのステージにあるか」「次にすべきアクションは何か」をリアルタイムで共有・確認できます。これにより、個人依存の案件管理から脱却し、チーム全体でのサポート体制が整います。
KPI達成状況のリアルタイムな可視化
訪問件数や受注件数などのKPIをリアルタイムでモニタリングできる点も、SFAの強みです。これにより、現場の行動と成果のギャップを素早く発見し、改善アクションをすぐに打つことが可能になります。PDCAサイクルの高速化に直結するため、成果に直結する運用が実現します。
顧客情報・履歴管理はCRMが得意
一方でCRMは、営業以外の部門も含めた顧客対応全体の質を底上げするツールです。単発的な商談データだけでなく、顧客の背景や過去の対応履歴、問い合わせ内容などを網羅的に管理できます。ここからはCRMで実現できる代表的な内容をいくつかご紹介します。
カスタマーサポート・満足度向上につながる活用
CRMはサポート部門との連携にも強みを発揮します。顧客からの問い合わせ履歴やクレーム内容、対応メモなどを蓄積することで、過去のやりとりを踏まえたきめ細やかなサポート対応が可能になります。これが顧客満足度の向上やLTV最大化に繋がります。
問い合わせ・対応履歴の一元化による属人化防止
CRMに情報が蓄積されることで、「担当者が変わったら何もわからない」といった属人化リスクを回避できます。対応履歴を参照すれば、誰が対応してもスムーズに顧客へのアプローチを再開可能です。結果として業務引き継ぎの効率化にも寄与します。
顧客ステージごとのアプローチ最適化
CRMでは、顧客ごとのライフステージ(新規・見込み・契約中・休眠など)に応じたアプローチが可能です。メール配信やキャンペーンも自動化されている場合が多く、タイミングを逃さず、最適な接点を設計できる点が強みです。
営業とマーケティングの連携を見据えたツール選定が鍵
SFAとCRMはそれぞれ独立して活用することも可能ですが、近年ではMA(マーケティングオートメーション)との連携を含めた一貫した顧客データ活用が求められています。特に、営業・マーケティング部門を横断するデータ連携が鍵となります。
リード獲得から商談化までを一気通貫で追跡可能に
マーケティング施策で得たリード情報をCRMに取り込み、商談化の進捗をSFAで追跡することで、リード発生から受注までのプロセスをシームレスに把握できます。これにより、部門間の分断を防ぎ、営業機会の最大化が図れます。
MAツールとの連携で実現するスコアリングとナーチャリング
CRMとMAツールの連携により顧客の行動ログに基づいたスコアリングやステップメールの自動配信が可能になります。温度感の高い見込み客を効率的に抽出し、営業部門へのパスもスムーズに行えます。
ツール間のデータ連携による顧客体験の統一
すべての顧客接点データを統合管理することで、顧客にとって一貫した体験を提供できるようになります。メール、電話、チャット、サポートなど、どのチャネルでも「同じ対応」が可能となり企業としての信頼感にも繋がります。
部門別・目的別で見るSFAとCRMの違い
SFAとCRMの違いを理解した上で、実際にどの部門でどのように使われるのかを具体的にイメージすることが導入成功の鍵となります。ここでは、営業・マーケティング・カスタマーサクセスなど、各部門の業務内容に応じてSFAとCRMの適性を整理していきます。
また、両者を連携させて活用することで得られる部門横断的な相乗効果についても解説します。導入を検討中の方は自社の組織構造と照らし合わせながらご覧ください。
営業部門にはSFAの利用が最適である
営業部門では顧客と直接接点を持ち、案件を前進させる業務が中心です。そのため、営業活動の可視化と案件進捗の管理が可能なSFAは非常に相性が良いといえます。
具体的には以下のような業務にSFAが貢献します。
- 日々の訪問・架電履歴の記録と分析
- 商談ステータスや受注確度のトラッキング
- 個人およびチーム単位のKPIモニタリング
- 売上予測と行動データの比較分析
営業活動を「見える化」しどのアプローチが成果に繋がっているかを定量的に評価することで、再現性のある営業プロセスを構築できます。属人化しやすい営業業務において、SFAは営業力の底上げを実現するための必須インフラです。
マーケティング部門・カスタマーサクセスにはCRMが有効
マーケティング部門やカスタマーサクセス部門では、「顧客との関係性の構築・強化」がミッションです。このような部門にとって、顧客情報の一元管理や行動履歴の把握が得意なCRMは最適なツールとなります。
主な活用シーンは以下の通りです。
- メルマガ配信やキャンペーン施策におけるセグメント管理
- 顧客ごとの対応履歴の蓄積と共有
- 顧客ステージごとの施策設計(例:見込み顧客→成約→リピート)
- サポート対応の履歴管理・応対スピードの改善
特にLTV(顧客生涯価値)を最大化するには、CRMを活用して一人ひとりに合った対応や継続的なコミュニケーションを設計することが不可欠です。CRMは長期的な信頼関係の構築に貢献するツールだといえるでしょう。
SFAとCRMの連携で得られる相乗効果
SFAとCRMはそれぞれ単独でも機能しますが、連携させて運用することでより高い効果を発揮します。
たとえば、以下のような連携によって業務がスムーズになります。
- マーケティング部門がCRMで取得したリード情報を、営業部門がSFAで引き継いでアプローチ
- SFAで蓄積した商談の失注理由をCRMで分析し、再アプローチのタイミングをマーケ側で判断
- 顧客満足度や対応履歴をCRMで把握し、クロスセルやアップセルにSFAを活用
こうした情報の連動により営業・マーケティング・サポート間の壁をなくし、顧客にとって一貫した体験(CX)を提供できるようになります。
参照:カスタマーエクスペリエンス(CX)とは?類似用語との違いやCX向上のための方法を解説!
SFAとCRMの導入メリット・デメリット
SFA・CRMは業務効率化・顧客対応の質の向上など多くのメリットをもたらしますが、同時に導入にはコストや運用面での課題も存在します。ここからはは、SFAとCRMそれぞれの導入による効果と想定される課題やリスクを整理し、導入判断の参考になるようにご紹介します。
SFA導入のメリットと想定される課題
SFAを導入することで営業部門における属人化の解消・活動の可視化・プロセスの標準化が実現できます。一方で、運用定着には工夫が必要です。
営業プロセスの可視化による属人化の解消
SFAを導入することで、営業担当者の行動や商談の進捗がすべてデジタル上に記録されるようになり、業務の「見える化」が進みます。これにより、特定の担当者にしか分からない属人的な営業スタイルから脱却し、組織としての営業ノウハウの蓄積が可能になります。
特に担当者が急に異動や退職をした場合でも、過去のアプローチ履歴や案件状況をすぐに引き継ぐことができ、業務の停滞や機会損失を防げるのが大きなメリットです。また、管理職もチーム全体の動きや成果をリアルタイムで把握できるため、個別支援や早期フォローがしやすくなり営業マネジメントの質の向上が期待できます。
行動データの蓄積とPDCAの高速化
SFAは営業活動の「いつ・誰が・何をしたか」を定量的に記録し、データベースとして蓄積していく仕組みを持っています。これにより、感覚や記憶に頼った振り返りではなく、実際の行動実績に基づく精度の高い分析が可能になります。
たとえば「提案数は多いが受注に結びついていない営業」「アプローチ頻度が少ない担当者」などを数値で明確に可視化できるため、個人単位でも組織単位でも改善点が見えやすくなります。
結果として、PDCAサイクルが回しやすくなり、組織としての営業力向上につながり、成功パターンを抽出してナレッジとして展開すれば全体の生産性も高まります。
運用定着までの負荷と教育コストの課題
SFAは多機能であるがゆえに、導入初期は「使いこなすまでに時間がかかる」「入力作業が面倒」といった声が現場から上がりやすいです。特に、営業担当者がこれまでアナログな手法で活動を記録していた場合、入力や操作に対する心理的ハードルが高くなり、結果的にSFAが「使われないツール」になってしまうケースも少なくありません。
そのため、導入時には段階的に機能を開放したり、マニュアルや研修を用意したりと、運用定着のための支援体制をしっかり整える必要があります。また、管理部門がツール運用のフォローを継続して行うことがSFAの長期活用と成果創出のポイントとなります。
現場からの反発を防ぐ導入アプローチの工夫
SFA導入時にしばしば起こるのが「管理目的で導入された」という現場の不信感です。特に営業現場では、日々の行動がすべて記録されることに対し「監視されている」と感じ、入力作業に消極的になるケースもあります。
こうした反発を防ぐためには経営層や管理職が「なぜSFAを導入するのか」「現場にどんなメリットがあるのか」を丁寧に説明し、共通認識を形成することが欠かせません。
また、SFAの設定や運用フローをトップダウンで決めるのではなく、現場の意見を取り入れながら設計していくことで、現場にとって「使いやすく役立つツール」として受け入れられるようになります。導入後も定期的にフィードバックの場を設け、柔軟に改善していく姿勢がとても重要です。
CRM導入のメリットと注意点
CRMは顧客情報を中心にすべての接点履歴を一元管理し、企業と顧客の関係性を継続的に強化するためのツールです。営業だけでなくマーケティングやカスタマーサポート部門まで活用できるため、顧客理解を深めた上での対応が可能になります。
一方でCRMをただ導入するだけでは効果は限定的であり、運用体制やルール作りが不十分だと、逆に情報の属人化やシステム形骸化につながるリスクもあります。
ここからはCRM導入のメリットと注意点をいくつかご紹介します。
顧客との継続的な関係構築によるLTVの向上
CRMを効果的に活用することで単なる一回きりの取引で終わらず、継続的な関係構築によって顧客のLTV(ライフタイムバリュー)を最大化することが可能になります。過去の購買履歴、問い合わせ内容、メール開封履歴、対応メモなど、あらゆる情報を蓄積・活用することで、顧客一人ひとりにパーソナライズされたアプローチができるようになります。
たとえば、再購入のタイミングに合わせたリマインド施策や過去のクレーム対応を踏まえたフォローアップなど、“一貫した顧客体験”の提供が差別化につながります。結果として、顧客のロイヤルティが高まり、口コミや紹介などの副次的効果も生まれやすくなることが期待できます。
マーケティング部門との連携で成果が最大化
CRMはマーケティング部門との連携によってその真価を発揮します。CRMに蓄積された顧客データを活用すれば、ターゲットセグメントの明確化や精度の高いメッセージ配信、購買ステージごとの適切な施策実施が可能になります。
特にMAツールと連携すれば、シナリオメールやスコアリング、パーソナライズ配信といった高度な施策も実行できます。
また、CRMから取得したデータをもとに過去の反応履歴を分析し、PDCAを素早く回すことで施策の精度が向上します。営業部門に対しても「ホットリード」を提供する形で、マーケ→営業の連携を強化し受注率を高める連携体制を構築可能です。
情報の入力・更新作業の属人化リスク
CRMの効果を十分に引き出すためには日々の情報更新が欠かせません。しかし、実務上は「入力が面倒」「誰かがやってくれているだろう」といった理由で、入力や更新作業が属人化してしまうケースも多く見られます。
このような属人化は情報の偏りやデータの欠損を招き、正確な顧客対応が難しくなるだけでなく、システムそのものへの信頼性も低下させてしまいます。
属人化を防ぐには全メンバーが自発的に情報を更新する文化と、ルールの整備が必要不可欠です。入力の自動化や簡略化(例:フォーム連携・ボイス入力)等を進めることで、業務負荷を減らし正確性と運用率を両立することもできます。
顧客接点が複数ある業務における設計の複雑さ
CRMはあらゆる顧客接点を一元管理することが前提となるため、顧客と接する部門が多い企業ほど、システム設計や運用ルールの複雑性が増します。たとえば、営業、カスタマーサポート、マーケティングの全部門がCRMを活用する場合、それぞれの情報入力項目や利用目的が異なるため、誰がどこまで入力すべきか、どの項目が誰にとって必要かを整理する必要があります。
また、過剰に多い入力項目は現場の負担となり運用が形骸化する要因にもなります。CRMを導入する際には利用部門ごとに役割を明確にし、必要最低限の情報に絞って運用設計を行うことが、定着と成果創出のための重要なポイントとなります。
よくあるSFA・CRM導入失敗の原因
SFAやCRMは業務効率化に大きく寄与する一方で、導入したものの活用されずに終わってしまう失敗事例も少なくありません。ここからは、実際の企業現場で頻発する「なぜうまくいかなかったのか」を4つの代表的な原因に分けて解説します。
これらの失敗パターンを事前に把握しておくことで、導入プロジェクトの成功率を高めることができるでしょう。
ツール導入を目的化したことでの形骸化
SFA・CRMの導入が「IT投資ありき」や「他社がやっているから」という理由でスタートしてしまうと、目的が不明確なままツールだけが先行し、現場では「なぜこれを使う必要があるのか」が共有されないまま形骸化してしまいます。
ツールはあくまでも業務課題を解決する手段であり、業務プロセスの見直しやKPIの明確化とセットで設計することが不可欠です。
たとえば「営業の属人化を解消する」「顧客対応履歴を残してLTVを上げる」といった導入目的が明確になっていない場合、現場の協力も得られず、結果的に入力がされない・使われないという事態に陥ります。目的設定と現場への徹底した共有が最初のポイントです。
社内ルールや業務フローとの不整合
SFAやCRMは既存の業務フローに合わない形で設計・導入されると、かえって混乱を招きます。たとえば、商談管理フローを変更せずにSFAを導入すると、入力タイミングや管理単位が実務とズレてしまい、「現場にとって使いづらいツール」として定着しません。
また、CRMで問い合わせ管理を行う際も、カスタマーサポートと営業部門で情報更新のルールが異なるとデータの整合性が取れなくなります。ツールを業務に無理やり合わせるのではなく、業務プロセスの見直しとセットで導入することが成功の条件です。
事前の業務棚卸しと関係部門との合意形成を十分に行った上で、ツールの導入に進みましょう。
ベンダー任せにしたままの初期設定・導入支援不足
導入時に外部ベンダーに丸投げした結果、自社業務への最適化がなされておらず、利用者にとって使いにくいシステムになっているという失敗も多く見られます。ベンダーは機能の説明やセットアップはしてくれても、実際の運用現場で「どのように活用されるか」までは細かく把握していないことが一般的です。
そのため、自社でどのような情報をどのタイミングで入力し、どの部門がどう参照するかといった「活用設計」は、企業側が主導して設計するべき領域です。
導入後の運用トレーニングやFAQの整備、ヘルプデスク体制の構築など、運用を見据えて必要な内容はベンダーに依存しない自社運用基盤の整備が不可欠です。
継続的な改善運用が行われず定着しない
SFAやCRMは「導入して終わり」ではなく、運用しながら現場の声を反映し使いやすく改善していくプロセスが重要です。特に最初の3〜6ヶ月間は、現場の利用状況を継続的にモニタリングし、「使いづらい」「入力項目が多すぎる」といった課題があれば速やかに改善することが求められます。
多くの失敗例では最初に作った設計をそのまま放置し、改善やフィードバックの場を持たないまま、いつの間にか「使われないツール」になってしまいます。利用率を可視化し、定期的にヒアリングを実施することで、運用の柔軟性と現場の納得感を両立し、定着率を高めることが可能です。
SFA・CRMの定着化に向けた4つのポイント
SFAやCRMを導入するだけでは意味がありません。真の効果を得るためには現場にツールがしっかりと定着し、日常業務の中で活用され続ける状態を作ることが欠かせません。ここからは、導入を成功させ運用を継続的に改善していくための実践的なポイントを4つに分けてご紹介します。ツール導入を“形だけ”で終わらせないために、ぜひ意識していただきたい観点です。
目的の明確化と導入前の課題整理がカギ
ツール定着の第一歩は「なぜSFA/CRMを導入するのか」という明確な目的設定と、それに基づいた現状課題の棚卸しです。
たとえば「営業活動がブラックボックス化している」「顧客対応履歴が共有されていない」など、現場が抱える具体的な悩みを可視化した上で、「この課題をSFAで解決する」「CRMで属人化を防ぐ」といった目的と手段の一致を図る必要があります。
目的が曖昧なままだと導入しても現場は納得せず、形骸化を招くリスクが高まります。また、関係部門と認識を揃えておくことで導入後の運用設計にも一貫性が生まれます。導入フェーズの設計こそが定着化の成否を分ける最重要プロセスです。
社内浸透を促す段階的なロールアウト
SFA・CRMの定着には「一気に全社導入」ではなく、スモールスタート→段階的な展開が有効です。最初は一部の営業チームやサポート部門など、業務が明確で運用効果が見えやすい部門から着手することで、早期に成果を出しやすくなります。
そこで得られたフィードバックや活用ノウハウをベースに、順次他部門へと展開していくことで、運用ルールや入力項目の標準化もスムーズに進められます。
また、初期導入部門で「ツールを活用して成果が出た」という成功体験を社内に共有することで、他部門への説得材料にもなり、自然と社内に浸透していきます。いきなり全体展開を目指すのではなく「試して学び、育てながら拡大していく」姿勢が重要です。
担当者教育とサポート体制の整備
SFAやCRMが定着しない理由のひとつに、「使い方が分からない」「エラーが起きた時に誰に聞けばいいか分からない」といったサポート体制の不足が挙げられます。導入時には、操作方法や活用ポイントを伝えるハンズオン研修やマニュアル整備が不可欠です。
また、現場が困ったときにすぐ相談できる社内のサポート窓口(システム管理者やIT担当など)を明確にしておくことで、心理的ハードルを下げ、継続的な利用を促すことができます。
さらに定期的な勉強会やQA共有会などを通じて、情報交換の場をつくることで自然と知識が広まりスキル格差を解消できます。「導入して終わり」ではなく、“育てて定着させる”という視点で運用体制を設計することが重要です。
利用率を定期的にモニタリングし改善PDCAをまわす
定着を実現するためにはツールの「利用状況を定量的に把握」し、「必要に応じて改善」するサイクルを継続的に回す必要があります。たとえば、ログイン頻度や入力件数、未入力項目の割合などを定期的に確認し、部署ごとの利用状況を可視化します。
活用が進んでいない場合はその原因をヒアリングし、「入力項目が多すぎる」「検索しづらい」などの課題をもとにUI改善やルール見直しを実施します。
また、改善結果を都度社内で共有し、運用改善が組織成果につながっていることを見える化することで、現場の協力も得やすくなります。運用体制を「見守り→改善→定着」のループで継続できるかどうかがSFA・CRMを組織に根付かせるポイントです。
参照:Salesforce定着化に向けた5つのハードル【資料ダウンロード】
SFA・CRMとMAツールとの違いとシステム連携で実現する全体最適
営業・マーケティング・カスタマーサポートといった部門ごとの施策を分断せず、一貫した顧客体験(CX)を提供するためには、各種ツールの適切な連携が不可欠です。ここでは、特にSFA・CRMと密接に関連する「MA(マーケティングオートメーション)ツール」に焦点を当て、役割の違いと導入順、システム連携のポイントを詳しく解説します。
MA(マーケティングオートメーション)の基本と役割
MA(Marketing Automation)ツールは見込み顧客(リード)へのアプローチを自動化・効率化するツールです。具体的には、Webサイトの閲覧履歴や資料ダウンロード、メルマガの反応といったオンライン行動をトラッキングし、それに応じたシナリオメールやスコアリングを行うことで、育成・選別されたリードを営業部門に引き渡す役割を担います。
CRMやSFAが「既存顧客や商談」を対象としているのに対し、MAは「まだ顧客になっていないリード」を管理・育成する点で明確な違いがあります。NAを導入することで営業部門の商談化率向上や、マーケティングROIの可視化が可能になります。リード獲得〜育成〜商談化までの前工程を自動化する武器として多くの企業で導入されています。
参照:マーケティングオートメーション(MA)とは?機能や選び方、おすすめツールまで紹介
MA×SFA×CRMの連携で実現する営業・マーケの一体化
3つのツールをうまく連携させることでリードの獲得から育成、商談化、契約、アフターフォローまでを一気通貫でデータ管理できる環境を構築できます。
たとえば、MAツールでホットリードをスコアリングし、一定のスコアに達した見込み顧客をCRMに連携することができます。その後、営業がSFAを通じてアプローチを開始し、進捗や成約情報を蓄積します。さらに商談結果をMA側へフィードバックすることで、どの施策が商談化につながったかを分析でき次回以降の施策に活かせるようになります。
このように3ツールの連携により、マーケティングと営業が分断されることなくデータを軸にした共通の指標で連携が可能となります。組織全体での営業効率と顧客体験の向上が期待できます。
3ツールの導入順と連携パターンの考え方
最近ではSFAとCRMが一体となって提供されているツールもおおくなってきましたが、一般的な導入の流れとしては、まず営業活動の可視化と管理基盤の整備のためにSFAを導入し、次に顧客情報を一元化し関係性を深めるCRMを追加、最後にリード獲得と育成の自動化を目的にMAを導入するのがセオリーです。
ただし事業フェーズや組織構造によって最適な導入順は異なります。たとえば、Webマーケティングに力を入れている企業では、最初にMAを導入しCRMとの連携によって効率的にホットリードを絞り込むケースもあります。
システム連携にあたっては各ツールが扱う情報の粒度や更新ルールの整合性を取ることが重要です。部門ごとの使い方の違いによってデータ構造がチグハグになってしまうと、逆に分析精度や活用度が下がってしまうため、連携設計時には「どの情報を誰が、どこで使うのか」を明確にしたうえで進める必要があります。
参照:MA導入を失敗させないための9つのポイント【資料ダウンロード】
自社に合ったツールを選ぶための判断基準
SFA・CRM・MAツールはいずれも業務効率化や成果創出に貢献しますが、自社の課題や事業モデルに合ったツールを選ばなければ期待通りの効果は得られません。ここからは、業種や業態、目的に応じた選定軸を整理し、自社に最適なツールを見極めるための視点をご紹介します。
業種・業態別に見るツール適性
企業が属する業界やビジネスモデルによってSFA・CRMのどちらがよりフィットするかは大きく異なります。
IT・SaaS業界では営業進捗の可視化が鍵となるSFA
ITやSaaS業界ではリード獲得から商談化、受注までのプロセスが明確に分かれており、営業の進捗や活動履歴を定量的に追跡する必要があります。特にインサイドセールスやフィールドセールスが分業されている企業では、SFAによる活動ログの蓄積とKPI管理が重要です。
また、営業活動の再現性を高め属人化を防ぐためにも、SFAは非常に相性が良いツールといえるでしょう。
不動産・保険業では顧客との長期に渡る関係構築を重視するCRM
不動産や保険といった業界では一度の商談で完結するのではなく、長期的なフォローアップやライフステージに応じた再提案が求められます。こうした業種では顧客との接点履歴や属性情報を詳細に管理し、最適なタイミングでアプローチするCRMが有効です。
過去の契約履歴や対応記録を元にきめ細かい提案ができることが成約率の向上に直結します。
店舗ビジネス・ECではCRMの分析機能が重要
BtoC業態である店舗ビジネスやECでは顧客の購買履歴やアクセスデータを活用し、顧客のニーズや行動パターンに応じた販促施策を設計することが成功の鍵となります。CRMは、顧客ごとのセグメント管理や、LTV分析、リピート促進施策の実行に長けており、マーケティングと連携することで高い効果を発揮します。
特に複数チャネルをまたいだ購入履歴や問い合わせ履歴を一元管理したい場合には、CRMやCDPの導入が推奨されます。
参照:CDPとは?導入でできることやメリット・デメリットをわかりやすく解説
目的別で考えるSFAとCRMの選び方
ツールの選定において最も重要なのは「何を実現したいのか」という目的の明確化です。以下に代表的な導入目的別の選び方を整理します。
営業効率の最大化を目指すならSFAの活用
営業活動の属人化を防ぎチーム全体での売上目標の達成を目指す場合には、SFAの導入が有効です。案件の進捗を見える化し、日々の活動をKPIに紐づけてマネジメントすることで、営業の質を均一化・効率化できます。
また、活動データに基づいた改善施策の実行や新人営業へのナレッジ展開にも繋がるため、組織全体の営業力強化に貢献します。
リピートやLTV向上を図るならCRM
既存顧客との関係性を深め継続的な売上やアップセル・クロスセルを狙う場合には、CRMの活用が不可欠です。問い合わせ対応、定期フォロー、誕生日キャンペーンなど、顧客に寄り添った施策を一貫して管理・実行できる基盤が整うことで、LTVの向上が見込めます。リピーターを増やすことで新規獲得コストを下げ利益率の改善にも繋がります。
新規リードの獲得からリードナーチャリングまで見据えるならMAとの連携も重要
「見込み顧客を増やしナーチャリングして営業に引き渡したい」という場合は、MAとの連携を視野に入れるべきです。MAで得たリード情報をCRMで管理しSFAで営業活動を追跡することで、リード獲得から成約までのプロセスを一元化できます。
これにより、マーケティング施策の効果検証や、営業部門との連携強化が進み、全社的な売上向上を実現できます。
主要なSFA・CRMツールの特徴
SFAやCRMと一口に言っても国内外には数多くの製品が存在します。それぞれに機能や価格、サポート体制などの違いがあり、自社に合った製品を選ぶためには各ツールの特徴を比較・把握することが重要です。ここからは利用企業が多い3つの代表的な製品を取り上げ、その機能や導入メリットを紹介します。
Salesforce|SFA・CRM・MAを統合した高機能プラットフォーム
Salesforceは世界No.1のシェアを誇るCRMプラットフォームであり、SFA・CRM・MAすべての機能を包括的に提供できる点が最大の強みです。商談管理・顧客管理・メールマーケティング・分析ダッシュボードなど、あらゆる業務に対応可能で、大企業から中堅企業まで幅広く利用されています。
また、カスタマイズ性が非常に高く、部門・業種ごとに必要な項目やプロセスを柔軟に設計できます。一方で、初期導入コストや運用負荷はやや高めなため本格的に業務改革やDXを進めたい企業向けのツールと言えるでしょう。豊富な連携アプリ(AppExchange)も魅力です。
参照:Salesforce(セールスフォース)とは?製品群や機能、メリット・デメリットを簡単に解説!
Zoho|中小企業に人気のコストパフォーマンス重視型
Zoho CRMは手頃な価格帯と使いやすいUIで人気を集めているSFA・CRMツールです。メール送信・リード管理・顧客管理・営業レポートといった基本機能を網羅していながら、月額数千円レベルで利用可能な点が魅力でスタートアップや中小企業に最適です。
特にテンプレートベースで簡単にセットアップできることから、「初めてCRMを導入する」「現場への負担を最小限にしたい」という企業におすすめです。
一方、Salesforceのような複雑なワークフローやカスタマイズは難しく、あくまでシンプルな活用を想定した構造になっています。多言語・多通貨にも対応しておりグローバル展開企業にも対応可能です。
HubSpot|SFA・CRM・MAが一体化したオールインワンプラットフォーム
HubSpotは、CRMを無料から提供しているマーケティング起点のプラットフォームです。MA機能に強みを持ち、Webトラッキングやステップメール、CTA管理などが標準装備されており、見込み顧客の獲得から商談化、成約、サポートまで一貫した顧客管理が可能です。
ノーコードでの操作性やUIの洗練さも高く評価されており、ITリテラシーの高くないチームでもすぐに使い始められるのが魅力です。営業向けのSFA機能、カスタマーサポート向けのチケット管理機能も搭載しており、マーケティングを軸に、営業やCSまで横断的にツールを揃えたい企業に向いています。
一方で大規模なプロセス自動化や複雑な権限設計が必要な場合には機能が限定されることもあるため、導入前に要件整理が重要です。
まとめ
SFAとCRMはどちらも営業・顧客対応の効率化を支える重要なツールですが、その目的や活用領域には明確な違いがあります。SFAは営業プロセスの可視化・標準化に強みを持ち、営業成果を組織的に向上させる武器となります。一方、CRMは顧客との継続的な関係性を築き、LTVの最大化やリピート施策の最適化に大きく貢献します。
また、MAとの連携を含めた全体最適を意識すれば、マーケティングから営業、サポートまで一気通貫でデータ活用が可能となります。
自社に合ったツールを選定するには、まず解決したい課題や部門ごとの業務特性を明確にし、それぞれのツールの特徴と照らし合わせて判断することが重要です。
とはいえ、自社だけでは導入検討及び定着化に向けた各施策を検討するのは困難なことも多いのが実情です。ストラでは、SFAやCRMについての導入検討から実際のシステム導入、活用支援まで一貫したご支援を実施することが可能です。
SFA・CRMの導入や活用についてお困りごとがありましたら、是非お気軽にご相談ください。
また、ストラのSFAやCRM支援についてさらに詳しく知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介しています。
マーケティングについてのお困りごとはプロにご相談ください
- 営業プロセスの可視化のためにツールを導入したいが、自社に合うツールが分からない
- 顧客管理の効率化のためにツールを導入したいが、自社に合うツールが分からない
- ツールを導入したが、使いこなせていない・定着化しない

執筆者 代表取締役社長 / CEO 杉山元紀
大学卒業後、株式会社TBI JAPANに入社。株式会社Paykeに取締役として出向し訪日旅行者向けモバイルアプリ及び製造小売り向けSaaSプロダクトの立ち上げを行う。
アクセンチュア株式会社では大手メディア・総合人材企業のセールス・マーケティング領域の戦略策定や業務改革、SFA・MAツール等の導入及び活用支援業務に従事。
株式会社Paykeに再入社し約10億円の資金調達を行いビジネスサイドを管掌した後、Strh株式会社を設立し代表取締役に就任。
▼保有資格
Salesforce認定アドミニストレーター
Salesforce認定Marketing Cloudアドミニストレーター
Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagementスペシャリスト
Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント
Salesforce認定Sales Cloudコンサルタント
Salesforce認定Data Cloudコンサルタント